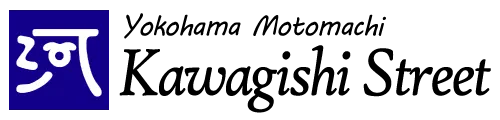HPを作るにあたり、「河岸の歴史も入れよう」となったのだけど
『河岸通りの歴史』なのか『河岸通り会の歴史』なのかで書き方も変わる。困った困った。
明治ごろの写真を持っていそうな人に、どうしようかな、と訊ねると
「今、良い展示やってるから観て来なさいよ」と促されたのがこれ。
いや、明治ごろの写真が欲しかったのだけど、貰えなかった。忙しくて探してられないんだって。
はーい、勉強してきまーす、と行ってきました。

横浜都市発展記念館で展示されていた『運河で生きる』展。
写真だけあっても知識が無いと書けないからね。入館料は800円。
物見雄山的に「どれどれ」と薄暗い部屋を見渡し、壁一面に貼られた展示物に目を通す。
1853年(嘉永6年) ペリーが浦賀にやって来る。
と書かれていた。
「ぺ、ペリーだと?? 河岸通りごときの歴史が、ぺ、ペリーに繋がっているだと??」
歴史の教科書では見たことがあったけれど、自分が今いる場所がペリーと関わっていたことに驚きました。
そうだった。ここは横浜。河岸通りと言えど元町。元町は横浜。
河岸通りの中の人アルアルで、すっかり横浜であることを忘れていた。
それも中区。関内関外の関外にあたる元町河岸通り。河がなくちゃ物流が始まらない時代からある河岸通り。
1859年(安政6年) 横浜開港整備
まさか自分が『安政』という単語を使うことになるとは。ビビりながらメモを取る。
横浜が開港したことで河の整備も始まって行く様がよくわかる展示だった。
ペリー、凄い。日本を動かした。横浜を動かし、河岸通りも動かした。
『海外への輸出にともなって運河としての河の活用が盛んになり、河岸通りに面する堀川も橋が架かり整備され、動き出していく。周りに押される形で物事が動いていく河岸通りの歴史はペリーから始まっていたならば、今の河岸通り会も河岸らしいのだな、と腑に落ちる。『川』ではなく『河』と呼ぶのはこの頃からか。』
感想を書き留めながら、矢印にいざなわれ進んでいく。
1871年(万延元年) 堀川の浚浚及び拡張工事
1890年(明治23年) 前田橋を鉄橋に架け替え
1893年(明治26年) 西之橋を鉄のトラスト橋に架け替え
1926年(大正15年) 関東大震災復興工事で西之橋をコンクリート製の橋に架け替え
1927年(昭和2年) 関東大震災復興工事で谷戸橋をコンクリート製の橋に架け替え
知っている河、知っている橋の名前が出てきて、目が離せない。
関東大震災の復興の時に、橋をガッチリ架け替えていたお陰で1945年(昭和20年)の横浜大空襲にも耐えたのか、と思うと感慨深い。
でもこれは河の歴史、橋の歴史だなぁ、どうするかな、と唸りながら進んでいくと河岸通り5丁目で運送業を営んでいた人の写真があった。
「鳥羽伏見の戦いの後、」と始まり、眩暈がした。歴史の教科書は本当に歴史を記したものなのだ、と改めて思う。
開港に伴い、全国から人が集まった。その1人が元町の河岸の5丁目で一旗揚げた。それが山本繁次郎だった。
繁次郎についてはHPの編集の都合以上、『河岸通りの見どころ 番外編』に入れることになった。
さて、河岸通り会の歴史はどこからだろう。
1984年(昭和59年) 高速道路横羽線開通に伴い、自動車通行可能道路開通、代官橋・市場通り橋増設、河岸通り植栽工事及び電柱照明工事完了
やっぱり、ここだ。高速道路ができ、車道が整備され、植栽帯・照明が点いた。
明治のころの運送関係者が集う河岸通りとは変わって行ったのは、ここが分岐点だった。
ここからが河岸通り会の歴史になって行きます。続きは『元町河岸通りヒストリー』をどうぞ。
『河岸通り会の歴史』でまとめたので歴史の教科書には載っていない事ばかりです。
中の人のぼやき節ばかりだけれど、これはこれで河岸通りの歴史のひとつなのだと思う。